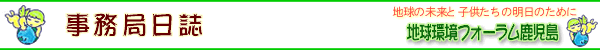
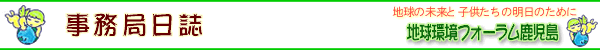
| ����C�܂܂ȁw�����Ǔ����x�ł��B ���E������肩�猒�N�@�܂ŕ��L�������Ă��܂��B |
| ���ߋ����O�͂����灨�@2003�N�@8���@�@9���@�@10���@�@11���@�@12���@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ 2004�N�@1���@�@2���@�@3���@�@4���@ �@5���@�@6�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ 7���@�@8���@�@9���@�@10���@�@11���@�@12�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2005�N�@1���@�@2���@�@3���@�@4���@�@5���@�@6�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@7�� �@8���@�@9���@�@10���@�@ |
| �Q�O�O�T�^�P�Q�^�Q�U�i���j | ���N�������b�ɂȂ�܂����I |
| �{���ŁA���N�̎����Ǔ������Ō�ƂȂ�܂��B ���N�͂Q���ɁA�@�l�o�^���u�m�o�n�@�l�n�����t�H�[�����������v�ƂȂ�A�P�O�N�ڂɂ��ĐV�����X�^�[�g���܂����B ���͂P�T���A�P�U���Ɣ��s�A�u�t�h���˗�����U�O�������A�����O�ōu�������Ă��������܂����B���̑��ɂ��A���낢��Ȃ��ƂŊ�Ƃ�s���A�����đ��̂m�o�n�c�̂Ɗ������s���Ă��܂����B ���͔N�X���������`�����Ă��܂��B �������A�l�̈ӎ���s���E��Ƃ̑Ή��́A�N�X�O�����ɂȂ��Ă���̂͊m���ł��B �Q�O�O�U�N���A�w�n���̖����Ǝq�������̖����̂��߂Ɂx�A��l��l�������̗���ŁA�ł��邱�Ƃ�t����Ă�����悤�ɂȂ�����Ȃ��Ǝv���Ă���܂��B ���N���A���낢��Ƃ����b�ɂȂ�܂����B ���N���A�ǂ�����낵�����肢�������܂��B |
| �Q�O�O�T�^�P�Q�^�Q�T�i���j | �ŋ߂̃G�R�j���[�X���ꂱ�� |
| �����ԕ���U���k���A���C�ȊO�͕��N��菭�Ȃ߁@���ȗ\�� �@���Ȃ͂Q�O���A���t�̃X�M�ƃq�m�L�̉ԕ���U�\���\�����B�k���A���C�n���������Ĕ�U�ʂ͕��N��菭�Ȃ��ƌ����A���Ɋ֓��b�M�z�n���ł͕��N�̔������x�ŁA�j��ň��ƌ���ꂽ���t�ɔ�ׂĂP�T�����x�ƌ�����ł���B��U�ʂ����Ȃ����R�́A�ԉ肪�`�������V���̋C���Ɠ��Ǝ��Ԃ����N������������߂Ƃ����B �i�����V���j ���r�o�g����łb�n�Q�팸�ց@�ĂV�B�A���{�ɔ��� �ăj���[���[�N�B�ȂǓ����V�B�͂Q�O���A���d������r�o������_���Y�f�i�b�n�Q�j�r�o�ʂ��A�r�o�g������x���g���č팸����u�n�扷�g���K�X�h�~�\�z�i�q�f�f�h�j�v�̊o���ɒ����B���B�̃p�^�L�m���i���a�}�j�������Ŗ��炩�ɂ����B �����ɂ��ƁA�����x���g���b�n�Q�̔r�o�ʍ팸���`���t����̂́A�č��ł͏��߂ĂƂ����B�u�b�V�������́A�Čo�ςɈ��e����^����Ƃ��āA�n�����g���h�~�̂��߂̋��s�c�菑���痣�E���Ă���A�V�B�͐����ɔ�����|���b�n�Q�팸�Ɍ����ϋɓI�ȑ����錋�ʂƂȂ����B�\�z�͂Q�O�O�X�N�P���P���ɊJ�n���A�e�B�͂P�g���P�ʂłb�n�Q�̔r�o�����o���B �i�����ʐM�j �����e�탊�T�C�N���@�����Ǝ҂�����x���@�������ŏI���� �y�b�g�{�g���Ȃǂ̗e��A��̍ė��p���߂��e�����T�C�N���@�̌������ŁA���Ȃƌo�Y�Ȃ͂Q�S���A���T�C�N����p�S����X�[�p�[��H�i���[�J�[�Ȃǂ̎��Ǝ҂��A�����̂̕��ʉ���E�I�ʕۊǂ̔�p���ꕔ�x�����鐧�x��n�݂��邱�Ƃ荞�ŏI���Ă��ł߂��B�����̂̓w�͂ɉ����Ďx���z��z������B �i�����V���j ���g�����h�d�C�����܂���A�r�o�b�n�Q�ɏ���c���� ���Ȃ͗��N�x�A�����E�����ւ̒��ɂŎg���d�͂��w������ہA���d���ɏo���_���Y�f�i�b�n�Q�j�̗ʂɏ����݂��A���̊�����d�͋Ǝ҂���D�ɎQ�������Ȃ����Ƃ����߂��B�d�͐��Y�̒i�K�łb�n�Q�r�o�}����_���B����A���Ȓ��⎩���̂Ȃǂɂ��������Ăт����Ă������j���B ���Ȃ́A���ɂŎg���d�C�̎��Ǝ҂�N�x���Ƃɓ��D�Ō��߂Ă���B���d�ɔ����b�n�Q�r�o�͐��͂⌴�q�͂ł͂قƂ�ǂȂ��̂ɑ��A�Η͔��d���ł͓����d�͗ʂ����ۂɑ����̂b�n�Q���r�o�����B�Η͂ł��A�V�R�K�X��Ζ��ɔ�אΒY��R�₷�Ƃb�n�Q�͑����o�邪�A�ΒY�͈������߁A��N�x�̎g�p�ʂ͂P�X�X�O�N�x��Ŗ�Q�E�W�{�ɑ����Ă���A�d�͗ʓ�����̂b�n�Q�r�o�ʂ͑S�̂ő����Ă���̂����B �d�͔̔��ɂ��ẮA�����d�͂ȂNJ����̓d�͂P�O�ЈȊO�̓���K�͓d�C���Ǝ҂��A����ȏ�̓d�C���g������҂ɔ̔��ł���d�͎��R�����i��ł���B �i�ǔ��V���j |
| �Q�O�O�T�^�P�Q�^�Q�P�i���j | �����ł��� |
| ���N�̓~�́A�������犦�g���K��Ă���B���{�A�ǂ����P�Q���ɂ��ẮA�v�X�̊����ɐk���Ă���悤���B �������i���オ���Ă��邽�߂ɁA�������l�オ��B���̕��A�G�A�R���ȂǓd�C�Œg���Ƃ�ƒ낪�����Ă���悤���B�G�A�R�����g���A���R�d�C�オ�����邵�A���d�̂��߂�������̃G�l���M�[���g�����ƂɂȂ�B �́A�N�Ԃ̓d�C�g�p�ʂ́A�~�͉Ăɔ�ׂăO���Ɖ������Ă������A�ŋ߂͂���قǂł��Ȃ��Ȃ��Ă���B����́A�~�̒g�[�Ɠd�@�킪�e�ƒ�ɕ��y���Ă���̂��A�傫�ȗv���̂悤���B ���̊����̒��A�G�A�R���g�p���䖝���邱�Ƃ��Ȃ��Ǝv�����A�ł��邾�������ނ��ƁB�����āA���X���x���オ�肷���ĂȂ����A���ȃ`�F�b�N������̂���Ȃ��ƁB �����̓~���́A�܂��S���e�n�Łu�P�O�O���l�̃L�����h���i�C�g�v�����{�����B�Ď��Ɏ����ŁA���₸���Ԃ�蒅���Ă����C�x���g���B�����ł��Ɩ��������A�e���r�������A�p�\�R���������E�E�E�Â��Ȗ���y���݂������̂��B�ł��A���N�̓G�A�R���͏����Ȃ������B �������������́A�V�C�\��Ő�}�[�N���t���Ă����B��������ɂȂ肻���ł��B |
| �����̃G�R�j���[�X�F���A�̐��E�C�ۋ@�ցi�v�l�n�A�{���W���l�[�u�j�͂P�T���A�Q�O�O�T�N�́A�ߑ�I�ϑ����n�܂����P�W�U�P�N�ȍ~�A���E�̔N�ԕ��ϋC�����Q�Ԗڂɍ����N�ɂȂ肻�����Ƃ̒������ʂ\�����B�P�X�U�P�N�|�X�O�N�܂ł̕��ρi�P�S�E�O�x�j�Ɣ�ׂO�E�S�W�x���������B�v�l�n�ɂ��ƁA�C�ʉ��x���㏸���ُ�C�ۂ̌����ƂȂ�G���j�[�j�����ۂ͍��N�R���܂łɏ��������A���E�e�n�ō������L�^���N�ԕ��ϋC���̏㏸�ɂȂ������B�I�[�X�g�����A���O��̂Ȃ��g�����N�ƂȂ錩���݂ƂȂ����ق��A��A�W�A��k�āA�쉢�A�����A�k�A�t���J�ŔM�g�Ȃǂ����������B�ē암�Ȃǂɑ傫�Ȕ�Q���o�����n���P�[���ɂ��āA�v�l�n�̃W�����[�����ǒ��͋L�҉�Łu���g�������͂ȃn���P�[���̕p�ɂȔ����ɂȂ����Ă��钛����v�Əq�ׂ��B �i�����ʐM�j |
| �Q�O�O�T�^�P�Q�^�P�V�i�y�j | �������A���̑f���炵���������I |
| �w�������s������c�x��Â̊��u���w�n���̂߂��݁@�������̎��R�̑f���炵���x�ɎQ�����Ă����B �u�t�͎��唎���يْ��̑�،��F�搶�B�n���w�҂炵���ڂŁA���܂Ŏ����m��Ȃ������������̑f���炵���������Ă����������B �f�w�ƒn�`�≷��̊W��A�э]�p�̕s�v�c�A�������̊��ΎR�i�����ɂP�P������j�̘b�ȂǁA���e�͑���ɓn��A�������낢�b�������������Ă����������B �����A���C�Ȃ���炵�Ă��鏊�ł��A�ӊO�ȁg�̘b�h�ɐS����������A�h�Ђ̖ʂ���͎������s���́A���Ȃ�댯�ӏ����������Ƃ��킩�����B ���R�̑f���炵�����ڂ̎������B���������A����������������y����ł݂����Ȃ��Ǝv�����B ����������w�������������ق̂g�o |
| �����̃G�R�j���[�X�F�A�X�x�X�g�i�Ζȁj���N��Q�̋~�ϐV�@���̍H���ł̔�U�h�~���@���c�_����V���|�W�E�����P�V���A�����s���ŊJ����A��Q�҂̎x���c�̂���͋~�ϐV�@�̓��e���s�\�����Ǝw�E����ӌ����o���B�V���|�͌��Q������̑��k���������Ă��铌���ٌ�m���ÁB�s���c�̃����o�[��ٌ�m��v��P�O�O�l���Q�������B�s���c�́u�����E����x�E�A�X�x�X�g�Z���^�[�v�����̖���Y�i��t�́A�Z����Q�҂̈⑰�ꎞ������R�O�O���~�ƂȂ������Ƃɂ��āu�]���P�N�̊��҂́w�킽���̖��͂R�O�O���~���x�ƒQ�����B���҂�⑰�ɑ��Ăǂ̂��炢�̑��Q���������̂����Ԓ��������Ă��Ȃ��v�Ɣᔻ�B �i�����ʐM�j |
| �Q�O�O�T�^�P�Q�^�P�T�i�j | �ŋ߂̃G�R�j���[�X���ꂱ�� |
| �����A�g�s�[�Ɍ��ʁ��k�C���t���Y�̂������y���g�����ǂ��i�����V���j �k�C���t���Y�̂������y���g�����ǂ��A�g�s�[���畆���Ɍ��ʂ����邱�Ƃ��A�l����ȑ�i�É����l���s�j�Ƒ��Z��[�J�[�A�p�i�z�[���i�{�ЁE���{�L���s�A�c�K���F�В��j�̌����O���[�v�̒����ŕ��������B�l����ȑ�a�@�Œt���������y���g�p�����a����������Ƃ���A���҂̏Ǐ��P�����Ƃ����B �������y�͊C���̑��ށi�A���v�����N�g���j�̎��������A�C��ɒ��N�ɂ킽���đ͐ρi���������j�����S�y��̓D�y�B���Ђɂ��ƁA�t���Y�̂������y�́A�n�w���n���ƔM�ɂ�鈳�͂������ߕώ����A�ׂ����C�E�������ł��Ă���B���̂��߁A���ɔ�ׂāA��������K�X�z�������D��A�z�����͈�ʂ̂R�{�ɂ����B ���Ђ͂O�R�N���烊�t�H�[���p���ނƂ��āA�t���������y�����������Ȃǂɍ����ĕǂɓh�z�����Ƃ���A�ڋq����u�A�g�s�[���������v�Ƃ̐�����ꂽ�B���̂��߁A����Ƌ��͂��A��N�P�O�����甼�N�Ԍ��������B �t���������y��ǂɓh�z�����a���ŁA���҂U�l�ɂQ�T�ԓ��@���Ă��炢�A�Տ��f�[�^�𑪒肵�A�a���O�̊��҂U�l�Ɣ�r�����B���̌��ʁA�X�g���X�̎w�W�ɂ͕ω����Ȃ��������A����݁A�畆�̔�����ȂǂR���ڂʼn��P���݂�ꂽ�Ƃ����B�t���������y�������̎��x��}�������ƂŁA�A�g�s�[�̌����̈�ł���_�j�A�J�r�Ȃǂ����ɂ���������ʂ��������Ƃ݂���B �����w���畆�Ȃ̑���_�����́u�A�g�s�[���畆���ɔY�ސl�ւ̘N��ƍl����B���P���ʂ̃��J�j�Y���𖾂�i�߂Ă��������v�Ƃ��Ă���B���Ђ͒t���������y��h�����ǂ����t�H�[���Z����łȂ��A�V�z�ɂ��L���Ă������j�B �����E�͉ߋ��Q�Ԗڂ̒g�����@���{�P�Q�ԖځA���g�����e�� �i�����ʐM�j �C�ے��͂P�S���A�Q�O�O�T�N�̐��E�Ɠ��{�̕��ϋC���̑���l�i�P�|�P�P���j�\�����B���E�̕��ϋC���͕��N�i�P�X�V�P�|�Q�O�O�O�N�̕��ρj���O�E�R�R�x�����A�L�^���c��P�W�X�P�N�ȍ~�łP�X�X�W�N�̃v���X�O�E�R�V�x�Ɏ����Q�Ԗڂ̍����ƂȂ錩���݁B ���{�͕��N���O�E�S�O�x�����A�P�W�X�W�N�ȍ~�P�Q�Ԗڂ̋L�^�ƂȂ錩�ʂ��B�����͍����̌����ɂ��āi�P�j��_���Y�f�i�b�n�Q�j�Ȃǂ̉������ʃK�X�̑����ɔ����n�����g���i�Q�j���N���琔�P�O�N�ŌJ��Ԃ���鎩�R�ϓ��̍������|�������Ă���B �����ɂ��ƁA���ɍ����������͖̂k�吼�m�A�k�ē����A�V�x���A�A�k���ȂǁB���ʕ��ϋC���ł͂X�����ߋ��ō��ŁA�S�|�V�����Q�Ԗڂ������B ���A�X�x�X�g�A�n�����Ė��Q�������c���Ȃ��@�������i�ǔ��V���j �����̉�̂Ŕ�������A�X�x�X�g�i�Ζȁj�ܗL�̌��z�p�ނȂǂ̏������@�ɂ��āA���Ȃ́A���ݍL���s���Ă��閄�ߗ��ď�������A�����ŗn�����Ė��Q�����鏈���ւ̈ڍs�𑣂����Ƃ����߂��B ���N�̒ʏ퍑��ɔp���������@�̉����Ă��o����B ���Ȃɂ��ƁA����A������̂ȂǂŔ�������A�X�x�X�g�ܗL�p�����́A�N�Ԗ�P�O�O���g���Ƃ݂��A�ŏI�I�ɂ͂S�O�O�O���g�����x�ɒB����Ƃ݂��Ă���B �A�X�x�X�g�͂P�T�O�O�x�ȏ�̍����ŏ�������Ƒ@�ۂ��n���Ė��Q���ł���B���Ȃ́A���Ԃ����L���鍂���̗n�Z�F�ł̏����𑣂����ƂŁA���Q���ɉ����A���ߗ��ď����ʂ��R���̂P���x�ɍ팸�ł��A����ɘH�ՍނȂǂɂ��ė��p���邱�Ƃ��\�Ƃ��Ă���B |
| �Q�O�O�T�^�P�Q�^�P�P�i���j | �|�X�g���s�c�菑 |
| �P�O���A�J�i�_�̃����g���I�[���ŊJ����Ă������s�c�菑����c�ƋC��ϓ��g�g�ݏ���\���������������B ���s�c�菑����߂Ă��Ȃ��Q�O�P�R�N�ȍ~�̉������ʃK�X�̍팸�̐�������A�c�菑���y���Ă��Ȃ��A�����J��팸�`���̂Ȃ��r�㍑���܂߂��S�����Q�����ċ��c���s�����B �A�����J�̏��ɓI�Ȏp��������A�ꎞ�͈Ïʂɏ��グ�����A������P���I�[�o�[����O����̌��ʁA�Ȃ�Ƃ����{�ȂNjc�菑���y������i���̔r�o�팸�ڕW�Ɋւ���c�_����ʉ��݂���06�N����J�n���邱�Ƃō��ӂ����B �������A�팸�ڕW�̋c�_�ɋ�̓I�Ȋ����݂͐��Ȃ������̂ŁA�B�����͎c�邪�A�Ƃ肠�����g����h���Ȃ��ōς����ł��A�e���Ƃ����ʂ͂������ƕ]�����Ă���悤���B �Q�O�P�R�N�B�B�B���ƂW�N��B���E�͂ǂ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ��낤�B ����Ł����팸�Ƙ_�c���Ă���ꍇ�ł͂Ȃ��Ȃ��Ă��邾�낤�B �Ƃɂ����A���H����̂݁B�����Ƃ₨��l���炠�ꂱ�ꌾ����O�ɁA�������͎������ŁA�ł��邱�Ƃ�����ł������A�����Ė����A�����邵���Ȃ��B |
| �����̃G�R�j���[�X�F���ې��̍q��@����P�N�Ԃɔr�o������_���Y�f�i�b�n�Q�j�̗ʂ��A���̑����ł����R�O�N�Ԃłقڔ{�����A�Q�O�O�Q�N�ɂ͐��E�œ��{�̑��r�o�ʂ̖�S���̂P�ɑ�������N�Ԗ�R���T�S�O�O���g���ɒB�������Ƃ��A���ۃG�l���M�[�@�ցi�h�d�`�j�̏W�v�łU���A���������B�r�o�͍�����������A�n�����g������w�������邱�Ƃ����O����邪�A�q�H�W���Ԃō팸�`����z���������Ȃǂ���A���s�c�菑�̋K���̑ΏۊO�B����́u�|�X�g���s�v�̉��g�����ő傫�ȏœ_�ɂȂ肻�����B�h�d�`�͊e���̍q��@�R���̎���ʂȂǂɊ�Â��Ĕr�o�ʂ𐄌v�B�O�Q�N�̔r�o���ł������������́A��T�P�O�O���g���̕č��őS�̂̂P�S�����߂��B�����Ń��V�A���Q�X�O�O���g���A���{�A�p���A�h�C�c�����ꂼ���Q�P�O�O���g���ŕ��B������ʂT�J���͂P�X�V�O�N��ȍ~�A�Q�{�ȏ�ɑ����Ă���B �i�����ʐM�j |
| �Q�O�O�T�^�P�Q�^�V�i���j | �G�C�Y�i�`�h�c�r�j |
| ���A���{�ł������A�R�l�ȏオ�G�C�Y�Ɋ����������Ă��邻���ł��B �P�Q���P���́u���E�G�C�Y�f�B�v�ł����B�G�C�Y�i�`�h�c�r�j�Ƃ́A�g�h�u�i�q�g�Ɖu�s�S�E�C���X�j�ƌĂ��E�C���X�Ɋ������邱�ƂŋN����a�C�ł��BHIV�́A�Ɖu�@�\��j�邽�߁A���܂��܂ȍۂ�E�C���X�Ȃǂ��̓��ɓ���₷���Ȃ�A���̊댯�������܂��B ���{�̂g�h�u���������͊m���ɑ������A�P�X�X�O�N��̂Q�{�ȏ�U�O�O���ȏ�ɂȂ��Ă��邻���ł��B�i�Q�O�O�S�N���ɂ͊��Ґ��R�C�Q�T�V�l�E�����҂U�C�T�Q�V�l�j �t�m�`�h�c�r�i���A�����G�C�Y�v��j�Ƃv�g�n�i���E�ی��@�ցj�ɂ��ƁA���݁A�g�h�u/�`�h�c�r�Ƌ��ɐ����Ă���l�͂Q�O�O�S�N���łR�C�X�S�O���l�A�Q�O�O�S�N�P�N�ԂŐV���Ɋ��������l�͂S�X�O���l�A�S���Ȃ����l�͂R�P�O���l�Ɛ��v����Ă��܂��B �G�C�Y�́u�����ɂ́A�S�R�W�Ȃ��a�C�v�ł͂Ȃ��A�Ƒ���e�ʁE�F�l����������\��������܂��B�܂��A�G�C�Y�����E�ɍ������������Ƃ����O����Ă��܂��B ���̃G�C�Y�ŖS���Ȃ����l�����A�����ĕa�C�ւ̗����Ǝx���̈ӎu���������߂Ɂw���b�h���{���x���g���Ă��܂��B���݁u���b�h���{���L�����y�[���Q�O�O�T�v���J�Ò��ł��B����x�A�G�C�Y�̂��Ƃ��u�m�邱�Ɓv����n�߂Ă݂܂��H ���u���b�h���{���L�����y�[���Q�O�O�T�v�Fhttp://redribbon.yahoo.co.jp/ |
| �����̃G�R�j���[�X�F���n�ŊJ�Ò��̋��s�c�菑��P�����c�i�b�n�o�^�l�n�o�P�j�łT���ߌ�i���{���ԂU�������j�܂łɁA�c�菑����߂Ă��Ȃ��Q�O�P�R�N�ȍ~�ɂ��ẮA�������ʃK�X�̔r�o�K���g�g�݂Ɋւ��ċc�_���n�܂����B���{�́u���ׂĂ̍����Q������g�g�݂ɂ��āA���N�̎����c�Ō������J�n���ׂ����v�Ǝ咣�����B�������A���c�菑�̔r�o�K�����Ă��Ȃ��č��┭�W�r�㍑�́A�V���Șg�g�ݍ��ɏ��ɓI���B�i�����V���j |
| �Q�O�O�T�^�P�Q�^�Q�i���j | ���g���h�~���� |
| �P�Q���́u�n�����g���h�~���ԁv�ł��B ���g���ɂ��e�������X�ɖ��炩�ɂȂ钆�A���������ł��邱�Ƃ́A��͂���X�̕�炵�̏ȃG�l�ƁA�G�R���C�t�����H���钇�Ԃ𑝂₷���ƂɏW���Ǝv���܂��B �P�Q�^�Q�Q�̓~���ɂ́A�܂��w�L�����h���i�C�g�x�̃C�x���g���e�n�ŗ\�肳��Ă��܂��B���̃C�x���g������łT��ځB�ȃG�l�ƃX���[�Ȗ�̐��i�̂��߁A����܂ł���������̂m�o�n���ƁA�����Čl�̕��X���Q�����A�����Ԃ�蒅�����Â��ɂȂ��Ă��܂����B �X�ɍ��N�́w�E�H�[���r�Y�x��������ɒ���A�n�ӍH�v���Ăł��邾���G�l���M�[���g�킸�ɁA�~���߂������Ƃ��������������ɂȂ��Ă��܂��B ���ꂼ�ꎩ���̂ł��鉷�g������A�ЂƂł��ӂ��ł��A���H���Ă����܂��傤�I ���S���n�����g���h�~���i�Z���^�[�@http://www.jccca.org/ �@�@�P�O�O���l�̃L�����h���i�C�g�@http://www.candle-night.org/ |
| �����̃G�R�j���[�X�F�D��h����_��Ɋ܂܂��u�W�E�����v�ȂǂR��ނ̉��w�������T���S�̐���Ɉ��e�����y�ڂ����Ƃ�n�ӏr���E������C�m�������������Ƃv�v�e�i���E���R�ی����j�W���p���̌����O���[�v���m�F�����B�n�ӏ�������́A�T���S�ʂ����E�X�G�_�~�h���C�V�Ƃ�����ނ̃T���S�́g�Ԃ����h��U�O�O�̂��e�������������C���łP�O���Ԏ��炵�A�e���ׂ��B�W�E�����́A�����e�n�ŊC���P���b�g��������P�O�O�����̂P�O�������x�����o����Ă���B���̔Z�x�Ŏ����������ʁA�T���S�ɋ������銌�������P�`�Q�����������B���������啝�Ɍ���ƁA�T���S�͎��ł���B�O���D���̓h���Ɏg����L�@�X�Y��A�_��Ɋ܂܂��L�@�����n�̃W�N�����{�X�ł��A���l�̈��e�����m�F���ꂽ�B�n�ӏ������́u�T���S�̎��Ō����ɂ́A�C�����̏㏸��I�j�q�g�f�A�ԓy�������������Ă��邪�A���w���������̈�ƍl������B���Ԓ����Ƒ���}���ׂ����v�Ǝw�E���Ă���B�i�ǔ��V���j |
| �Q�O�O�T�^�P�P�^�R�O�i���j | �����̊����� |
| �����̋g�яȁE�g�юs�łP�R���ɋN�����Ζ����w�H�ꔚ�����̂ɂ���́E���ԍ]�̉������}���Ɋg�債�A���ɑ傫�Ȗ��ɂȂ��Ă���B �L�Q�����������]�ȃn���r���s�̐����p�̎搅���ɒB���A��������������~�A���S���l�̐����ɐ[���ȉe�����o�Ă��邵�A����ɖʂ������V�A�ɓ��E�n�o���t�X�N�s�́u��펖�Ԑ錾�v���o���A�������瑹�Q�����̐\����������Ă���Ƃ����B ����̒����V���ł��A�Ռ��I�Ȏʐ^���f�ڂ���Ă����B�����̒����𗬂���́u�z���C�z�[�v�̐�ӂ������A�����Ă���ʐ^�������B���̖A�͐q��ȑ傫���A�����ł͂Ȃ��B�䂪�ڂ��^���悤�ȖA�ŁA���̉����q�����������ƕ@���������ĕ����Ă���B�����ƈ��L���A�����Ȃ��̂Ȃ̂��낤�B �����̍��Ɗ��ی쑍�ǂɂ��ƁA�s�s�𗬂���̂X�O������������A�V�T���̌��_�f���R��Ԃɂ���B���C�̐Ԓ������͂W�O�N��̂R�{�B�_���̂R���l�̈��������s�K�i�B�S���U�U�P�s�s�̂����A�R���̂Q�Ő��s���A�Ƃ�킯�P�P�O�s�s�Ő[���炵���B �z���C�z�[����ɂ́u���v�ƌĂ�鑺���_�݂��Ă�Ƃ̂��ƁB���������L����ǂނ����ŁA�����N���N�����Ă���B �u���E�̍H��v�Ƃ��Ĕ��W�𑱂��Ă��钆���B���������̈Õ��́A��m��Ȃ��قǐ[���B�ł��A����𒆍������̖��ɂ��Ă����̂��B���E�������̉���������邽�߂ɒ����ɉ������Ă���悤�ȋC������B |
| �����̃G�R�j���[�X�F��ɂō̎悵���X�����g���Đ̂̑�C���̂Q�_���Y�f�i�b�n�Q�j�Z�x���X�C�X�E�x������Ȃǂ̃`�[�������́A���݂̂b�n�Q�Z�x�͖�U�T���N�O�܂ł����̂ڂ��Ă��ߋ��ō��ł��邱�Ƃ����������B�Q�T���t�̕ĉȊw���T�C�G���X�ɔ��\�����B��ɂ̕X�����g�����ߋ��̑�C�̐������͂͂���܂Ŗ�S�S���N�O�܂Ői��ł���A�b�n�Q�Z�x�͂��͈̔͂Ō��݂̔Z�x���ō��������B����͂���ɂQ�P���N�����̂ڂ������ƂɂȂ�B�`�[���͓�ɓ����́u�h�[���b�v�ƌĂ��n�_�Ő[����R�Q�O�O���[�g���܂Ō@�킵�̎悵���X���́B��R�X���N�O�\��U�T���N�O�ɓ����镔���ŁA�����̑�C������߂��C�A�ׂ��B���̌��ʁA���̔N��̂b�n�Q�Z�x�͂P�W�O�\�Q�X�O�o�o���Ɣ����B�Y�Ɗv���ȍ~�ɋ}�㏸���A���݂͂R�W�O�o�o���ɒB�����b�n�Q�Z�x�́A�U�T���N�O�܂ł����̂ڂ��Ă��ߋ��ō��ł��邱�Ƃ����������B����̌��ʂ́A�C��ϓ��\���̐��x�A�b�v�ɂ��𗧂Ƃ����B �i�����ʐM�j |
| �Q�O�O�T�^�P�P�^�Q�V�i���j | �w�n���A����Ȃ����I�x |
| �u�k�̍�����v�ȂǂŗL���ȋr�{�ƁA�q�{��������E���o���肪�����x�ǖ�m�����Q�O�O�T�w�n���A����Ȃ����I�x�Ƃ����������Q�T���̖�A�s��ꂽ�B ���j��ɂ���ĖłсA���͋A��̋����Ȃ�������l�̉F���l�������A������ˑR�A�l�����ꂽ�R�̔я�œ����U�l�̘J���҂Ƙd���̏��̎q�̑O�Ɍ���܂��B ���ꂢ�Ȑ������߂Ēn���ɂ���Ă����̂ł����A���ׂĂ݂�ƃy�b�g�{�g���̐����R�̗N�������A�����Ēn���l�̑̂̒��̐����A���łɉ��w�����ɉ�������A��@�I�ɂ���Ƃ������Ƃ��������܂��B�����ŁA�ޏ����������ꂢ�Ȑ��̑���ɋ��߂����̂́E�E�E ���낢��ȃh�^�o�^������A�ŏI�I�ɒn���𗣂�Ă����Ƃ��ɁA�t�e�n�����M���Ă������b�Z�[�W���u�n���A����Ȃ����I�v�@ �ޏ������͒��N�A�F����f�r���Ă����̂ŁA���������̑c�悪���܂ꐶ���������͒m��Ȃ����A�n���ɍ~�藧���u���������C�����������v�ƌ����܂��B�����Ď��������̐��͖łтĂ��܂������A�ǂ����n���͓���������܂Ȃ��ŗ~�����Ƃ����C���������߂āA�Ō�̃��b�Z�[�W��`���Ă���܂����B �L���L���ʂĂ��Ȃ��F���A���̒��ɂ���ɁX�����ۂ��Ȑ��u�n���v �����ۂ��ł��n���͍��������Ă��邵�A�����������������ł��Ă����B ���܂ł��n�������葱����悤�ɁA���ׂĂ̐����������葱������悤�ɁA�������l�Ԃ͊F�A���̏d��ȋ`���ƐӔC������Ǝv���B |
| �����̃G�R�j���[�X�F�n�����g���h�~�̂��߂ɒg�[�ɗ���Ȃ����������Ăт�����u�E�I�[���r�Y�v�̃t�@�b�V�����V���[���Q�R���A�������s�̎R�`���ł������B�]�ƈ��炪���f���ƂȂ�A�g�����A�������Ȓ����Ȃ����Ă����B�E�I�[���r�Y�͍��Ắu�N�[���r�Y�v�ɑ����Ċ��Ȃ���Ă������g�݂ŁA�����̒g�[���Q�O�x�ɐݒ肵�A�g���������Œn�����g���h�~�ɖ𗧂Ă悤�Ƃ������g�݁B�t�@�b�V�����V���[�ł͎R�`���ɏo�X����v�X�u�����h���r�W�l�X�ƃJ�W���A���̏d�˒��X�^�C�����āB�O���낢�̃X�[�c��A�X�R�b�g�^�C�A�d�˒��ɍ���������̃Z�[�^�[�ȂǁA�t�@�b�V�������ƒg�����𗼗������������I�B�K�ꂽ�l�͏]�ƈ�����̃t�@�b�V�����V���[�ɔ���𑗂��Ă����B�i�����V���j |
| �Q�O�O�T�^�P�P�^�Q�S�i�j | �匵���̋e�܂� |
| ����A�������s�g�쒬�i��j�ɂ���w�匵���i��뉀�j�x�ɁA�v���Ԃ�ɍs���Ă����B���傤�ǁu�e�܂�v���J�Ò��ŁA���͋e�܂莩�̂͏��߂Ă��������A�Ȃ�ƍ��N�ł����S�U��ڂ𐔂����Ƃ����B �뉀���ɂ͗l�X�ȋe���N�₩�ɍ炫�ւ��Ă����B��{�̌s���牽�\�̂��Ԃ��炢�Ă�����́A�܂��l�Ԃ̓��قǂ̉Ԃ��炩���Ă�����́A�~�͂̏��̂悤�Ȏp�ō炢�Ă�����́B�܂��A���Ðĕj��F����q������Ă���E�l�����̋e�l�`���������B�ǂ��������A�т�����B �w�匵���i��뉀�j�x�́A���Â̂��a�l�̕ʓ@�B������z�R�ɁA�э]�p��r�ɂ݂��ĂȗY��Ȏ،i�뉀�B���߂Ēm�����̂����A�뉀���ɂ́u���d�p�̃_���Ձv���������B �H�̈���A�ۂ��ۂ��z�C�̒��A�̂�т�Ɖ߂������B�ʐ^�ŁA���̕��͋C�����ł������Ă��������B
|
||||||
| �����̃G�R�j���[�X�F�Đ��\�G�l���M�[���i�s���t�H�[���������{�i�����s�A�ȉ��q�d�o�v�j�Ƌ�B�d�͂������Ői�߂Ă����Z��p���z�����d�̓����x���E���͎��Ƃ̐��ʕ����܂Ƃ܂����B�����Ƃ�1999�N�x����6�N�Ԃ����čs�������̂ŁA���́A�����Ƃ���B�e�n�ő��z�����d�̕��y��傫���������Ƃ������ŁA���z�����d�ɂ��ƒ납��̗]��d�͂��W�߂邱�Ƃʼnď�̃s�[�N���̓d�͂�₤�ɂ͂܂��͕s���A�Ƒ������Ă���B�����Ƃ͋�d�Ǝs���c�̂��s�������̋������ƂŁA��d�������������g���q�d�o�v�����z�����d�V�X�e���̓����҂ɑ��z��~�̏��������x�o�B��B�e�n�ւ̃V�X�e�����y��i�߂����A���z�����d�̔��d���Ԃ�A�d�͋����ւ̍v���x�Ȃǂ����Ă����B���ɂ��ƁA99�N�x����O��3�N�Ԃ̎x�����ƂŁA��B�ŐV���ɐݒu���ꂽ�Z��p���z�����d�V�X�e���͖�430���B�㔼��3�N�Ԃ́A���z�����d�̗L�����Ȃǂɂ��Ē������s���u�G�߂ȂǂŔ��d�ʂɂ��������A�d�͂̋����v��̒��Ɉʒu�t���邱�Ƃ͓���v�Ƃ������̂́u���̎��Ƃ����������ɋ�B�̏Z��p���z�����d�̐ݒu������o�͂͑S���̓��߂�܂łɏ㏸�����v�Ƃ��Ă���B�܂���d�����̎��Ƃ��_�@�ɁA�Z��Ȃǖ�4��5��J���i04�N�x�j���瑾�z�����d�̗]��d�͂��w������Ɏ����Ă���B�i�����{�V���j |
| �Q�O�O�T�^�P�P�^�P�X�i�y�j | �ŋ߂̃G�R�j���[�X���ꂱ�� |
| ���C�m���ݖ��ŏ������@�x�R�s�œ�������� �i�����ʐM�j ���{�C�Ȃǂ̊C�m���ݖ��ɂ��āA���{�A�����A�؍��A���V�A�̂S�J���̐��Ƃ炪����������u��P��k�������m�n��ɂ�����C�m���݂Ɋւ��鍑�ۃ��[�N�V���b�v�v�i���ȂȂǎ�Áj���P�S���A�Q���Ԃ̓����ŕx�R�s�Ŏn�܂����B�P�T���܂Ő��{�W�҂⌤���҂������̎��g�݂Ȃǂ����B �Y�����݂Ȃǂ́A�i�ςȂ��ƂƂ��ɁA���ۑS�̖ʂ������莋����Ă���A��ɂ͍��ۋ��͂��K�v�Ȃ��߁A���A���v��i�t�m�d�o�j���i�߂���ۑS���̘͂g�g�݁u�k�������m�n��C�s���v��v�ɎQ������S�J�����W�܂����B ���A�W�A�̂��ݏ������x���@���ȁA���A�Ƃ��A�g �i�����ʐM�j ���Ȃ͂P�T���A�A�W�A�n��ł̋}���Ȍo�ϔ��W�ɔ����đ��������邲�݂��팸���邽�߁A�����ȂǂU�J����ΏۂɁA�팸�ʂ�T�C�N���ʂȂǂ̐��l�ڕW�荞�p���������v��̍�����x�����邱�Ƃ����߂��B �{�N�x���獑�A���v��i�t�m�d�o�j�Ȃǂ̍��ۋ@�ւƘA�g���āA�e���̔p���������̎��Ԓ����ɏ��o���A�Q�O�O�V�N�x�܂ł̌v������ڎw���B �S���ɓs���ŊJ���ꂽ�����N���X�ɂ��u�R�q�C�j�V�A�`�u�t����v�ŁA�p�����̔����}���Ȃǂɂ��Ă̍��ۋ��͂�\�������̂����[�u�B �Ώۂ́A�����̂ق��A�x�g�i���A�C���h�l�V�A�A�t�B���s���A�^�C�A�}���[�V�A�B�����v��ɂ́A�ƒ낲�݂�Y�Ɣp�����i�̌��ޗ��ȂǂɃ��T�C�N������ʂ�A�ŏI������Ɏ������ނ��݂̍팸�ʂȂǁA�e���̕K�v���ɉ��������l�ڕW�荞�ށB �����g���ŋ����s���`�@�ɐB�������萔������ �i�����ʐM�j �n�����g�����i�݊C��͐�̉��x���㏸����ƁA���̑̂��������Ȃ�����ɐB�����ቺ�����肷��ȂǁA���̐��E�ɑ傫�Ȉٕς�������Ƃ��������A���E���R�ی����i�v�v�e�j���P�W�����\�����B �v�v�e�́u���g���͗��l�Ȃǂɂ���Đ[�������Ă��鋙�Ǝ����̌����ɔ��Ԃ��|���A���E�̐H���s�������������邱�ƂɂȂ�v�ƌx�������B ���́A�����̕ω��Ƌ��̐��ԂɊւ���ߋ��̃f�[�^�≷�g���̏����\���Ȃǂ���ɁA�C��͐�A�Ώ��̉��x�㏸�����̐��Ԃɗ^����e���Ȃǂ͂����B �č���J�i�_���ӂ̊C��ŊC�����x�̏㏸���i�ނƁA�^����J���C�A�X�Y�L�Ȃǔ�r�I�ቷ���D�ދ��̎����ʂ��T�O���߂������A�k�C�̃^���Ȃǂ̕��z���傫���ς��B |
| �Q�O�O�T�^�P�P�^�P�V�i�j | ���g���ւ́u�K���v |
| �n�����g�����ɑ��ẮA�������ʃK�X�̔r�o��}������Ȃǂ́u�ɘa�v��ƁA�C��ϓ��̉e���ɑ���u�K���v�������A�g���ցh�Ƃ��Đi�߂邱�Ƃ��L�����B �w�ُ�C�ہx�Ƃ������t�͓��퉻���A���g���̉e����g�߂Ŋ�����悤�ɂȂ��Ă����B���E�ɖڂ�������ƁA���Ԃ͂����Ɛ[�����B���������āA�u�K���v�������}���K�v���o�Ă����B �K���K�v�Ƃ����ΏۂƂ��ć@�������i���p�̌������A�����ʂ̑����j�@�A�H���i�앨�̎�ނ�͔|�����̕ύX�j�@�B���݁i�h����Ȃǂ̂����グ�A�X�ё����ɂ�鉈�ݕی�j�@�C���N�i�㉺�����ݔ��̉��P�A�`���a�̌x���j�@�D���Z�i�o�σ��X�N�̕��U�j�A�Ȃǂ��l�����Ă���B�i�����V���Q�Ɓj �P�P���Q�W������A�J�i�_�̃����g���I�[���ŊJ�Â����u�C��ϓ��g�g���Q�O�O�T�N�����g���I�[����i�b�n�o�^�l�n�o�P�j�v�ł́A�K���Ɋւ���u�T�J�N��ƌv��v�����肳���\��Ƃ̂��ƁB ���g���ɑ����́A���}�ɁA�����ċ�̓I�ɍs�����Ƃ��A���X�����Ă���̂�������B���������A�W�Ȃ����Ƃł͂Ȃ��B���������̂��Ƃł͂Ȃ��A�����łɁA�������������ɓ����Ă��邱�Ƃ����o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |
| �����̃G�R�j���[�X�F�o�ώY�ƏȂ͂P�S���A�d����̗�g�[�⋋����ȂǏȃG�l���M�[�ݔ��𗈔N�R���܂łɐV�K�ɓ������钆����Ƃɑ��A�o��z�̔���������ɕ⏕����Ɣ��\�����B�S�Ǝ킪�ΏۂŁA�����R�O���ɐ\������ߐ�B��_���Y�f�i�b�n�Q�j�Ȃǒn�����g���K�X�̔r�o�팸�Ɍ����A�ݔ������̕��S���傫��������Ƃ��x������B���������ݔ��̂b�n�Q�팸�ʂ��O�ҋ@�ւ��F���A���̌�A�o�Y�Ȃ����݂����C���^�[�l�b�g�̎s��ŁA�b�n�Q�r�o�ʂ̎�����؎����ɎQ�����邱�Ƃ��A�⏕�̑O��ƂȂ�B���Ǝ҂ɂ͎��؎����̂��߂b�n�Q�̍팸�ڕW���߂Ă��炤���B���ł��Ȃ��Ă��Ԋ҂����߂Ȃ��B �i�����ʐM�j |
| �Q�O�O�T�^�P�P�^�P�T�i�j | �N�z���g�t |
| �������������s�́A�ō��C�����Q�P�x���Ă���B�P�P���̔��ŘA���Q�O�x���Ă���Ƃ́A�����犦���̂��C���Ȏ��ł��A�u���������C�����������Ăق����v�Ǝv���Ă��܂��B ���������A�������n�߁A�R�ԕ��ł͍g�t�̋G�߂ƂȂ��Ă��邪�A�����͂Ȃ�ƂȂ����r���[�Ȋ����B �g�t�́A�P���̍Œ�C�����W�x�ȉ��ŐF�Â��n�߁A�T�`�U�x�ɂȂ�Ƌ}�ɐi�ށB�C�ے��ł͒n�����Ƃɕ��n�ɂ������̃C���n�J�G�f�̖����߁A�̗t���قڂȂ��Ȃ����Ƃ����g�t���Ƃ��Ă���Ƃ̂��ƁB ����ł����ƁA�����̕��N��11��28���A��オ12���R���B���̓��ɂ����A���Ȃ�x���Ǝv�����A���N�́A���ꂩ��X��10���ȏ���x�������炵���B����́A�T�O�N�O�Ɣ�ׂ�ƂQ�T�Ԉȏ���x���Ȃ��Ă���B �u�t���g�t�v���߂��炵���Ȃ��悤�ɂȂ�A���Ƃ��ƍg�t�̒x�����ցA����A�������s�́A���N�A���N���30�`40�����x���A�����O�����߂��������B���N���A���̕��ł́A�u�N�z���g�t�v�́A�m���̂悤�ȋC������B ��������g���̉e���ɂ��Ǝv�����A�߂������A�������Ɂu�g�t���v��������O�ɂȂ�̂��낤���B |
| �����̃G�R�j���[�X�F���A���v��i�t�m�d�o�j�͂P�O���A�C���N�푈��p�ݐ푈�Ȃǂʼn��w�H�ꂪ�j�ꂽ���ƂȂǂɂ��A�C���N�Ő[���Ȋ��������L�����Ă���A�L�Q�p�����̏����Ȃǂɖ�S�O�O�O���h���i�S�V���~�j�̎������K�v���Ƃ�����\�����B���쐬�Ɋ֗^�����C���N�̃I�X�}�������͓����A�W���l�[�u�̍��A���B�{���Łu�T�O�O���|�V�O�O���l�̃o�O�_�b�h�Ƌߍx�̏Z���͐��ݓI�Ȍ��N���X�N�ɂ��炳��Ă���v�Ǝw�E�B�C���N�S�y�ŗE�����e�ɉ������ꂽ�ꏊ���R�P�P�J�����肳��Ă��邱�ƂȂǂ������u����Ƃ͂P�O�N�ȏォ����v�Ƃ��č��ێЉ�̋��͂����߂��B �i�����ʐM�j |
| �Q�O�O�T�^�P�P�^�P�R�i���j | �Y�p�̃��T�C�N�� |
| ���Ȃ͂W���ɁA�O�S�N�x�ɐV���ɂU�V�R���A�S�P���g���̎Y�Ɣp�����̕s�@���������������Ɣ��\�����B���̌��ʁA�������ꂸ�Ɏc�����s�@�����̎Y�p�ʂ́A�O�Q�N�x�̒����J�n�ȗ��ő�̂P�C�T�W�O���g���i�v�Q�C�T�U�O���j�ɒB�������ƂɂȂ����B���̗ʂ́A�����h�[���Ɋ��Z����Ɩ�P�R�t���ɂȂ�Ƃ̂��ƁB �Y�Ɣp�����Ɋւ��Ă͖������A�����ĕs�@�����Ƒ����̖��_���w�E����Ă��邪�A����ƕ���ō����ɂȂ��Ă��Ă���̂��u�p�����̃��T�C�N���v���B �Y�p�̍Ď������̓��������܂钆�A�V���ȗL�Q�����������Ă��܂�����A�̔��Ə̂��Ď��͏������Ă���A���ő��z�̂����������Ă�����E�E�E ���̔w�i�ɂ́A�ŏI������s���Ƃ����傫�ȉۑ肪����B���̃y�[�X�Ŕp�������o������ƁA������ŏ����ł���̂́A���ƂQ�N�ƌ����Ă���B������͕s�����A����ɔ����������i���}���B �p�^�C����������S���}�b�g�A�u�����K���X���g�����^�C���A�t�O����g�������|�i�A�Đ����y���g����������E�E�E�S���ŁA���낢��ȃ��T�C�N�����i���J������Ă���B�ǂ����A���ꂩ����{���Ɉ��S�ŗL�Ӌ`�ȃ��T�C�N�����i�݂̂�����A�g���Ăق����Ɗ肤�B |
| �����̃G�R�j���[�X�F�C�ے��͂P�P���A���E�̂P�O���̌����ϋC���i����̂݁j���A�L�^���c���Ă���P�W�W�O�N�ȍ~�̓����̕��ϋC�����O�D�W�Q�x����A�ߋ��ō��ɂȂ����Ɣ��\�����B���N�͌����ϋC���̍ō��l�X�V���������A�U���A�X���ɑ����ĂR��ځB����A���{�̂P�O���̕��ϋC���́A�L�^���c��P�W�W�X�N�ȍ~�̓����̕��ϋC�����P�D�S�R�x����A�X�W�N�Ɏ����ߋ��Q�Ԗڂ������B�����ɂ��ƁA���Ƀ��[���b�p��J�i�_�A�I�[�X�g�����A�����ȂǂŋC�������傫�������B�n�����g���ɉ����A���\�N�����ŌJ��Ԃ���鎩�R�ϓ����A�X�O�N��㔼���獂�����ɓ����Ă��邱�Ƃ������ƍl������Ƃ����B���{�͑����m���C���̐��͂������Ȃ��������Ƃ��A�����̈���ƂȂ����B �i�����V���j |
| �Q�O�O�T�^�P�P�^�P�P�i���j | �������� |
| �����̐V���Ɂw���E��Y�n���ۂ��ƃ_���ł����x�i�H�c�@���꓾�j�Ƃ�����������e����Ă����B�ǂu�ԁA�u��������Ȃ��A���̒n���̑S�Ă��A�㐢�Ɏc���ׂ��f���炵����Y����Ȃ��v�Ǝv�����B �u�����͐��E��Y�ɓo�^���ꂽ����f���炵�����v�A�������́u�����̌Â������v�E�E�E�݂����ɑI�ʂ�����̂ł͂Ȃ��A�{���͉��������A�ǂ������������f���炵���B�D��Ȃ����Ȃ��قǁA���̒n���ɑ��݂��Ă��邷�ׂĂ̂��̂������B �������A���̒n���ɑ��݂��Ă���S�Ă̐������A�A���������B �A���̃e����\���A�����E���́B���R�j����~�܂�Ȃ��B�B�B �������̖����A���R���A�ւ�ׂ��������̂Ƃ��āA����x�A���o�������B |
| �����̃G�R�j���[�X�F�g�t�̒����ω��X���ׂĂ݂�ƁA�T�O�N�O�ɔ�ׂăJ�G�f�̍g�t�͂P�T�D�U���A�C�`���E�̉��t�͂P�O�D�V���x���Ȃ��Ă��邱�Ƃ��A�C�ے����܂Ƃ߂������G�ߊϑ��łX�����������B�t�ɃT�N���̊J�Ԃ́A�S�D�Q�������܂��Ă���A�����́u�n�����g���Œ����I�ɋC�����㏸���Ă��邱�Ƃ��e�����Ă���v�Ɛ����A���コ��ɉ��g�����i�߂A���{�l�̋G�ߊ��ɂ��e����^���������B�����ɂ��ƁA�t�̓T�N���̂ق��c�o�L���X�D�S���A�^���|�|���U�D�O���A�J�Ԏ��������܂�A�Ăɍ炭�T���X�x���͂T�D�W���A���܂��Ă����B�T�N���Ɋւ��āA�����A���É��A���ȂǑS���̑�s�s�U�n�_�ƒ����s�s�̕��ς��r�����Ƃ���A�����s�s�̂Q�D�W���ɔ�ׁA��s�s�͂U�D�P���ƊJ�Ԏ����������Ȃ�X���������ŁA�����́u�q�[�g�A�C�����h���ۂȂǓs�s���ɂ��C���̏㏸���^�����e���̈�v�ƕ��͂��Ă���B �i�����ʐM�j |
| �Q�O�O�T�^�P�P�^�X�i���j | �����T�[�����ɓo�^ |
| ����A���������a���c�r�i�F������s�V���@���j�ƁA���v���i�c�l�i�㉮�v���j�̂Q�ӏ����A�����T�[�����̓o�^���n�Ɍ��肵���B�����������Ƃ��Ă͏��߂Ă̂��ƁB �����T�[�����Ƃ́A�Ώ���͐�A�����Ȃǎ��n�̕ۑS�ƌ����ȗ��p��ړI�Ƃ�����ŁA�������̂́u���ɐ����̐����n�Ƃ��č��ۓI�ɏd�v�Ȏ��n�Ɋւ�����v�Ƃ����B�P�X�V�P�N�̍��ۉ�c�ŏ�̑�����A�V�T�N�P�Q���ɔ������ꂽ�B���{�͂W�O�N�P�O���ɉ������A���H��������i�ȂǂP�R�J�������ɓo�^����Ă���B�i�S���E�ł̓o�^���n�͂P�S�V�J���̌v�P�T�Q�S�J���j �a���c�r�́A��̃x�b�R�E�g���{���������邱�ƂŒm���A�܂��i�c�l�͓��{��̃E�~�K���Y���n�Ƃ��ėL���ȏꏊ�B�ǂ�����s�������Ƃ����邪�A���i�͂ƂĂ����₩�ȏ����B ���݁A���E���Ŏ��n�͂ƂĂ��M�d�ȑ��݁B�������̎��n���A������@�ɂ��̑��݉��l��F�߂��A�X�Ȃ���ۑS�ɂȂ�������ȂƎv���B |
| �����̃G�R�j���[�X�F���{�́A���̓~�i�P�Q���`���N�R���j�̒n�����g���h�~��Ƃ��āu�~�G�̏ȃG�l���M�[��v���܂Ƃ߂��B�g�[���x�������͂P�X�x�A��Ƃ�ƒ�ł͂Q�O�x�̐ݒ�����߂�ȂǁA�g�߂łł���|�C���g��B�����ɂ�茵�������g�݂��ۂ��Ă���̂��������B�y�����^���u�N�[���r�Y�v�𒆐S�ɂ����ċG���ʂ����������Ƃɂ��₩��A�u�E�H�[���r�Y�v�������t�Ɋ��������낤�Ƃ����l�������A����������́u�炢�~�ɂȂ肻���v�Ƃ̐����R���B��́u���{�Ƃ��Ă̎��g�݁v�Ɓu�����ɑ��鋦�͗v���v�̂Q���\���B�����́i�P�j�g�[���x���P�X�x�ɐݒ�i�Q�j���x�݂͒��ɓ�����ď����i�R�j�Ȃ��O���ۂ̓p�\�R�������܂߂ɃV���b�g�_�E���i�S�j�ɗ͊K�i�𗘗p�i�T�j������P���j���̌��p�Ԏg�p�̎��l�\�\�ȂǁA����������������A�����Ɏ������Ƃ����_���B����A��Ƃ�ƒ�ɂ́i�P�j�g�[���x���Q�O�x�ɐݒ�i�Q�j�����Ԃ̃G���W�����������ςȂ��i�A�C�h�����O�j�ɂ��Ȃ��i�R�j���O�Ɩ��{�݂̐[��̏����E�����i�S�j�ʋ�W���[�ł̓S����o�X�Ȃnj�����ʋ@�ւ̗��p�\�\�Ȃǂ����߂Ă���B �i�����V���j |
| �Q�O�O�T�^�P�P�^�U�i���j | ���݁E�S�~��� |
| �ŋ߁A�Ăсu���ݖ��v�Ɋ֘A����j���[�X�������B�ŏI������̎c�]�N���͖�P�R�N�����Ȃ��Ƃ����Ă�������A�؉H�l�������ł���B �����ʉ����A�Ď������i�ށ@�O�R�N�x�̈�ʂ��ݔr�o�� �i�����ʐM�j �Q�O�O�R�N�x�̉ƒ낲�݂ȂLj�ʔp�����̑��r�o�ʂ������h�[����P�R�X�t���̂T�P�U�P���g���ŁA�O�N�x�Ƃقړ����ʂ������Ƃ��钲�����ʂ��܂Ƃ߂��B ���̂��������̂�Z��������E���T�C�N���������݂̎������ʂ͂X�P�U���g���ŁA�O�N�x���U�E�O�������������A�ŏI������ւ̖��ߗ��ėʁi�W�S�T���g���j�͂U�E�S�����������B ���Ȃ́u���T�C�N�����͔N�X���サ�Ă��邪�A���r�o�ʂ͂P�O�N�O���牡���X���������Ă���B���ʂȕ�������ȂǁA���݂̔��������炷�r�o�}���̎��g�݂��ۑ肾�v�Ƃ��Ă���B �������ݗL�������S���V�V�U�s��̂S�S�����{�@�{������ �i�����V���j �S���̑S�s�Ɠ����Q�R��i�v�V�V�U�s��j�̂S�S���i�R�S�P�s�j���A��ʉƒ낲�݁i�e�傲�݂Ȃǂ������j�̎��W�E������p�̈ꕔ��ŋ��Ƃ͕ʂɒ�������L���������{�ς݂��A����ς݂ł��邱�Ƃ������V���̒����ŕ��������B�������������\����P�R�D�S���i�P�O�S�s�j����A�L�����͍�����L���錩�ʂ����B�ƒ낲�ݏ����͎����̂̋Ɩ������A���Ȃ͍��N�T���A�����ʂɗL�����Ƃ��āu�L�����v��p���������@�̊�{���j�ɐ��荞�݁A���g�݂𑣂��Ă����B �L���������s�ɂ����ʌ��ʂ����Ƃ���A�����R�O�T�s�̂U�P�D�U���i�P�W�W�s�j���u���ʂ��������v�Ɠ������B����A�P�U�D�P���i�S�X�s�j�́u���ʂ͈ꎞ�I�������v�A�P�D�U���i�T�s�j�́u���ʂ͂Ȃ������v�Ɖ��A�L�������K�����������ʂɂȂ���Ȃ������������B ���g���̂ėe������点�@�R�[�q�[�X�Ȃǂƌ��ʋ��� �i�����ʐM�j �R�[�q�[�V���b�v��t�@�X�g�t�[�h�X�Ŏg���̂Ă��鎆�R�b�v�Ȃǂ̗ʂ����炷���߁A�X���ŌJ��Ԃ��g����e��̗��p���i���߂����勦������Ǝґ��ƌ��ԕ��j���ł߂��B�ΏۂƂ���Ǝ��X�܂̖ʐςȂǂ��ƊE�c�̂ȂǂƋl�߁A�Q�O�O�V�N�x�܂łɋ�������ԍl�����B�@ |
| �����̃G�R�j���[�X�F���A���v��i�t�m�d�o�j�͂��̂قǁA�A�t���J�嗤�̌��������Ő[���Ȋ�@�ɂ��炳��Ă���Ƃ̕\�����B�t�m�d�o���P�X�W�O�N��A�X�O�N��ƋߔN�̉q���ʐ^���r�����Ƃ���A���P���A�t���J�ő�̒W���r�N�g���A�̐��ʂ��A�X�O�N�㏉�߂Ɣ�ז�P���[�g���Ⴂ���Q�������A�t���J�̃`���h���ߋ����\�N�łP�O���̂P�ɏk�������\�\�Ȃǂ��N���ɂȂ����B��Ȃ��̂����łU�V�V����Ƃ����A�t���J�嗤�̌̑����ŁA���ʌ�����̏k���������A�j�W�F�[���ł͉ߋ��Q�O�N�ŒW���̎��n�̂W�O���ȏオ���ł����B�͐����͊��������A�u���̒n�悪�s���艻���鋰�ꂪ����v�Ƃ��A���������Đ[���ȍ��ƊԂ̑Η���Փ˂��N����\�����w�E���Ă���B �i�ǔ��V���j |
| �Q�O�O�T�^�P�P�^�S�i���j | �ƒ낲�݂̕s�@���� |
| �R���r�j�̂��ݔ��ɉƒ낲�݂��̂Ă���g��Q�h���G�X�J���[�g���A���s���ł͂��ݔ��̌�������X���o�n�߂��Ƃ����B�������A���̌��ۂ͐�䂾���̂��Ƃł͂Ȃ��B �ƊE�ő��̃Z�u���\�C���u���E�W���p���͂W�����{����A�S����P���P�O�O�O�X�̂��ݔ��Ɂu�ƒ�p�̂��݂̎������݂͂��f�肵�܂��v�Ƃ̃X�e�b�J�[���āA���ݖh�q����Ƃ��Ă���Ƃ̂��ƁB �����P�U�N�x�̊������ɂ��ƁA�w���ݏW�Ϗ��ȊO�ł��A�R���r�j��X�[�p�[�A�w�A�����̂��ݔ��̎����A�͐�A���H���ɁA�����̌`�ԁi���W�܂ɓ����������݂�d�C�X�g�[�u�P�Ƒ|���@�P��Ȃǁj���猩�Ė��炩�Ɍl�ɂ����̂Ǝv����s�@�������펞�������A�ƒ낲�݂␔�����̑e�傲�݂Ȃǂ��̂Ă��Ă��܂��B�������H�̃p�[�L���O�G���A��T�[�r�X�G���A�ł͖�Ԃɂ��ݔ����ӂ̂ق����ԏ�≀�n�̐A�����݂̊Ԃɂ��݂��̂Ă�ꂽ��A�͐�ł͐�p���H�̍ۂ�쌴�A�l�ڂɂ��Ȃ����̉��ɂ��݂��̂Ă��Ă��܂��B �܂��A�p�����̕s�@�����Ɋւ�������͔N�X�������Ă���A����14�N�x�̋����͖�P���S�猏�ɏ���Ă��܂��B���̂�����ʔp�����ɌW����̂��S�̖̂�74�����߂Ă���A�����ł��Y�Ɣp������傫�������Ă��܂����B��ʔp�����ɂ͈��H�X����r�o����鐶���݂Ȃǎ��ƌn�̔p�������܂܂�Ă��܂����A���̑����͉ƒ납��r�o�������̂ł���A�l�ɂ��s�@�����̐��̑����������Ă��܂��B�x J-SaPa ���H�T�[�r�X�@�\�ɂ��ƁA�w����16�N�x��J-SaPa�̃G���A���甭���������݂́A��13,064t�B���̂Ȃ��ɂ́A�ƒ납��̐����݁A�e���r�E�①�ɁE���Ȃǂ̑e�傲�݁A���z���ނȂǁA�������H�O����̎������݂���61.0%�܂܂�Ă��܂��B �@J-SaPa���A���������������݂��݂��������邽�߂ɂ���������p�́A�N�Ԗ�11���~�B���̔�p�́AJ-SaPa���T�[�r�X�G���A�̃��X�g�����Ȃǂ̉^�c�ɂ�蓾�������Řd���Ă���A�������H�����̒��Ɋ܂܂����̂ł͂���܂���B���݂����Ȃ��Ȃ�A���̔�p�ŃT�[�r�X�̏[���E���オ�}����悤�ɂȂ�܂��B�x �S�����X�܂ŁA���ݎ��W�Ԃ�����Ă��Ă����Ƃ����b�܂ꂽ���ɏZ�݂Ȃ���A�ǂ����Ă���قǂ܂łɉƒ낲�݂̕s�@�����������̂��낤�B���́A�s�v�c�łȂ�Ȃ��B |
| �����̃G�R�j���[�X�F���Ȃ͂R���܂łɁA������ȂǂŎg���Ȃ��Ȃ������Ί�����[�J�[��������A�c�����������Ζ�܂�V�������Ί�Ƀ��T�C�N�����鐧�x�𗈔N�R���܂łɑS���œ������邱�Ƃ����߂��B������̏����̔�p�́A���T�C�N�������Ƃ��ď��Ί�̔̔����i�ɏ�悹������j�B���[�J�[���͏�悹���͂P�{�Q�O�O�O�~���x�ƌ�����ł���B�̔����O���ɏ��܂ł͊�Ƃ�ƒ납��������ۂɏ�����p�Ƃ��ď�悹���Ɠ��z������l�����B���T�C�N���ɎQ������̂́A���{���Ί�H�Ɖ�̉������[�J�[�̂����A���Q�Ђ��܂ތv�S�ЁB�ƒ�Ȃǂŕs�v�ƂȂ������Ί�̏����͂܂��܂����B�L���܂��͖����Ń��[�J�[��������邩�A�����̂ɂ���Ă͗L���ʼn������Ƃ��������B�i�����ʐM�j |
| �Q�O�O�T�^�P�P�^�P�i�j | �ŋ߂̃G�R�j���[�X���ꂱ�� |
| �����{�̔N���ϋC���A�Q�P�O�O�N�ɂ͂Q�\�R�x�㏸ �i�ǔ��V���j �C�ے��͂Q�W���A���E�Ɠ��{�̒����I�ȋC��ϓ���ُ�C�ۂ̗\���ƕ��͂��܂Ƃ߂��Q�O�O�T�N�Łu�ُ�C�ۃ��|�[�g�v�����\�����B ���E�̔N���ϋC���͉ߋ��P�O�O�N�ԂŖ�O�E�V�S�x�㏸���Ă���A�Q�P�O�O�N�ɂ́A����ɂQ�E�T�x�㏸�A���{�̔N���ϋC�����Q�`�R�x�㏸����ȂǂƗ\�����Ă���B ���|�[�g�ɂ͔N���ϋC���̏㏸�̂ق��A���P���k�ɂ��ɂȂǂ̐��E�S�̂̊C�X��̖ʐς����N�Q���ɉߋ��ŏ����L�^���Q���C���㏸�ɔ����C���̔M�c���ŁA���{�̍�N�̊C�ʐ��ʂ͉ߋ��P�O�O�N�̕��ς����U�E�V�Z���`�����Ȃ����\�\�ȂǁA�n�����g�����𗠕t����ϑ����������荞�܂ꂽ�B �܂��A�P�O�O�N��̓��{�ł́A�قƂ�ǂ̒n��ŔN�~���ʂ��������A�����Ƃ���ł͖�Q��������Ɨ\���B�P��������~���ʂ��P�O�O�~���ȏ�ƂȂ��J���A�����̒n��ő�����Ƃ��Ă���B �C�ے��C����ۂ́u�ߋ��P�O�O�N�̐��E�̔N���ϋC���̏�ʂS�ʂ܂ł��A�ŋ߂P�O�N�ɏW�����Ă���B�������ʃK�X�̉e���ȂǂŁA��������g���X���͑������낤�v�Ƃ��Ă���B���|�[�g�́A�Q�N���ƂɌ��\����Ă���u�n�����g���\�����v�ȂǁA�C�ے��̊e�퓝�v�������܂Ƃ߂����̂ŁA�P�X�V�S�N�ȗ��A��T�N���Ƃɍ쐬���Ă���B ��������ǎQ���͂V���@�m�o�n�Ő��_���� �i�����ʐM�j ���t�{�͂Q�X���t�Łu���Ԕ�c���c�́i�m�o�n�j�Ɋւ��鐢�_�����v���ʂ\�����B����ɂ��ƁA��ʎs������̂ʼnc����ړI�ɂ��Ȃ��m�o�n�̂悤�Ȋ����ɂ��ĂV�X�E�V�����u��v�ƕ]���������ŁA�ߋ��T�N�Ԃɂm�o�n�����Ɂu�Q���������Ƃ�����v�̂͂V�E�Q���ɂƂǂ܂��Ă��邱�Ƃ����������B �����ł́A���̂P�N�Ԃ̊�t�o���ɂ��Ă�����B���炩�̊�t���������Ƃ�����l�͂V�O�E�T���ɏ��A���z�͂P�O�O�O�~�������S�T�E�W���ƍł����������B�����A�m�o�n�ɑ����t�҂͂S�E�O���������i�����j�B �m�o�n�����ɎQ���������Ƃ��Ȃ��Ɠ������l�̗��R�́u����������@��Ȃ��v���g�b�v�łT�O�E�T���B�����łQ�X�E�U�����u�m�o�n�Ɋւ����Ȃ��v���������B�Q���o���҂ł́u�F�l��m�l�ɗU��ꂽ�v�Ƃ̉��ł������S�W�E�X���������B�Q��������������́u����҂��Q�҂̕����E���v���R�V�E�O���A�u���R���ی�A���T�C�N�����i�v�Q�Q�E�Q���Ȃǁi������������j�B �����ΖȔp��������N�x�͂P���W�R�R�S�g���@���� �i�����V���j ��U���₷�������t���A�X�x�X�g�i�Ζȁj�p�����̍�N�x�̔r�o�ʂ́A�S���łP���W�R�R�S�g���ɏ�������Ƃ��R�P���A���Ȃ̂܂Ƃ߂ŕ��������B�S���̔r�o�ʒ����͖�P���S�O�O�O�g���������P�X�X�X�N�x�ȗ��Ŗ�S�O�O�O�g�������������ƂɂȂ�B ����A���Ȃ��V�`�X���A�ΖȔp�����̔r�o�Ǝҁi��̋Ǝҁj����W�^���ƎҁA�����Ǝ҂Ȃǂɗ������茟���������ʁA�����t���ΖȂłQ�S���A���U���̐Ζȓ��茚�ނłX�R���̕s�K�؎��Ⴊ�������B���ɔ��U���̐Ζȓ��茚�ނł́A�V�[�g�����⎼���Ȃǂ̔�U�h�~�O�ꂳ��Ă��Ȃ����Ⴊ�ڗ����A���Ȃ́u���U���ł���̂��ăo���o���ɂ���ƁA�ΖȂ���U���鋰�ꂪ����̂ŁA��U�h�~���O�ꂷ��悤�w���������v�Ƙb���Ă���B |